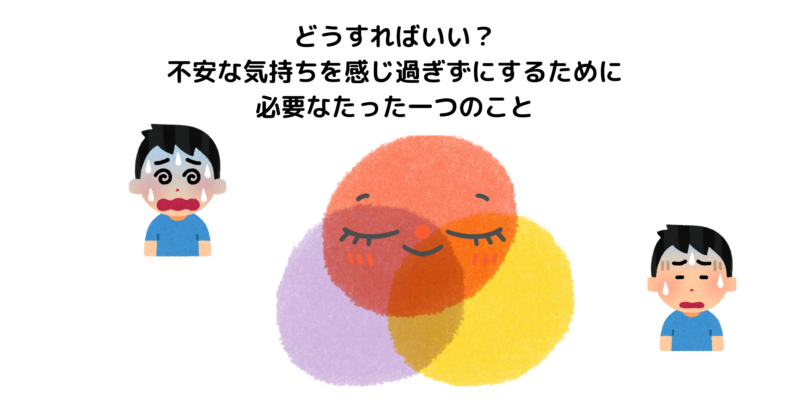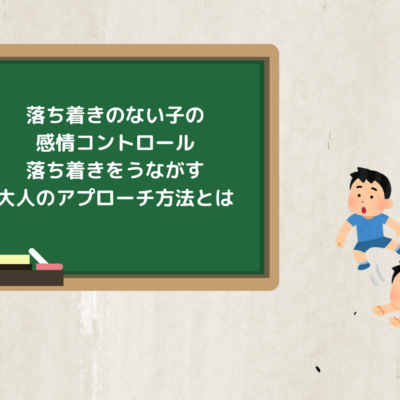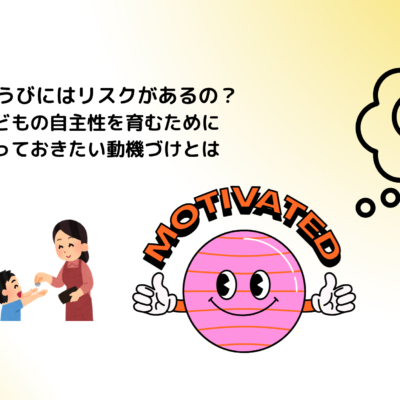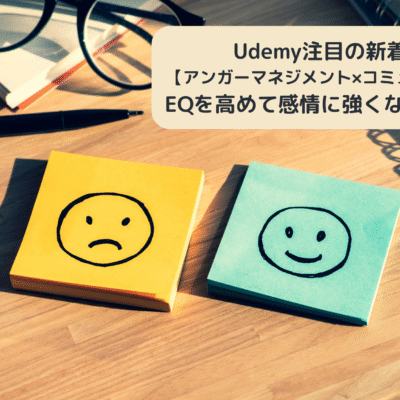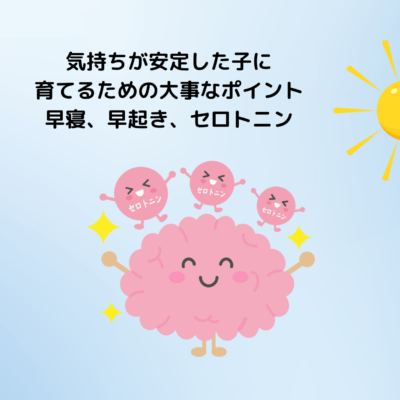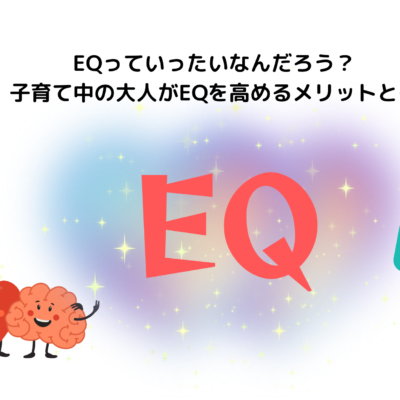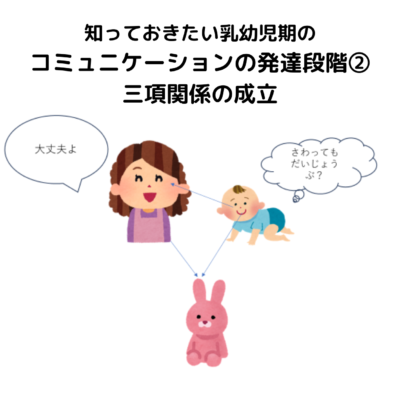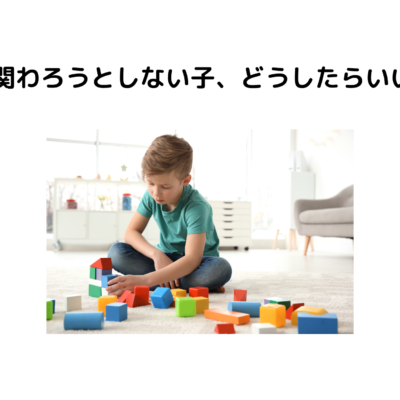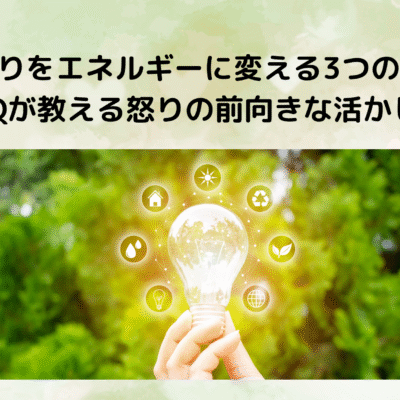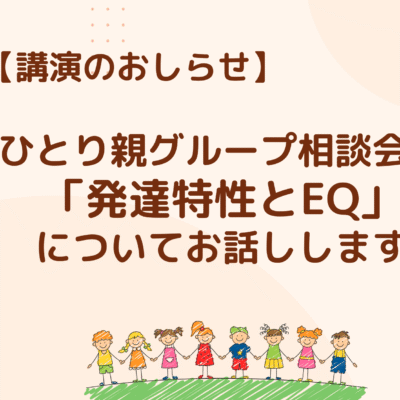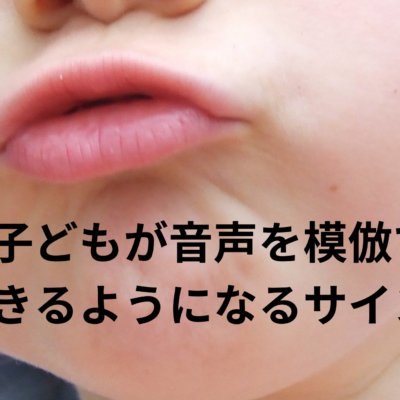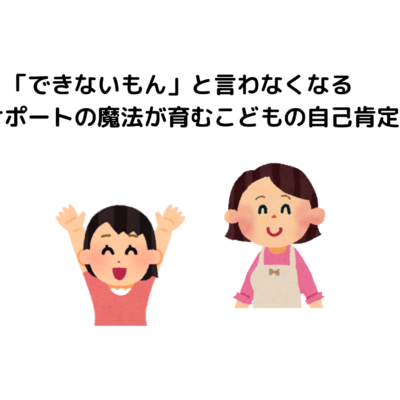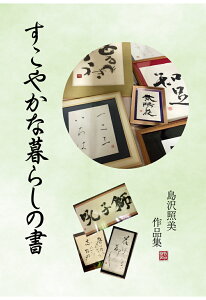不安を感じすぎて困っているという悩みを抱えている人は、思いのほか多いものです。
特にコロナ禍以降、子どもたちの間でも不安の強さを訴える子が増えました。
どうすれば、不安を感じすぎずに穏やかになれるのか
不安になる原因と、対処法をご紹介します。
「不安」の役割とは何か
「不安」は危険がせまっているという危機感と関係しています。
原始時代、ヒトの生活は常に危険と隣り合わせでした。
生き残るために、逃げたり戦ったりといった行動をすぐ起こせるよう「不安」感情は必要不可欠なものだったのです。

現代の生活においても、「不安」を感じるからこそ、立ち止まって考えたり、誰かに相談したりして、慎重に物事を進めることができるのです。
不安を感じすぎてしまうのはなぜ?
このように正しく反応が起きれば、「不安」はとても大切なものです。
しかし、必要以上に「不安」を感じすぎてしまうと、いつもざわざわして落ち着かないですよね。
生活に支障がでてしまうこともあります。

なぜ、そのようなことが起きてしまうのでしょう。
不安な気持ちを押さえつけるとどうなる?
どんな気持ちもみな波のようなもの。
常に揺れ動いています。
「不安」な気持ちを感じたら、
「ああ、今、自分は不安に感じているな」
と受け入れると、数分もたてば落ち着いてきます。
しかし、そこで「不安なんか感じちゃだめだ」「もっとポジティブにならないと」
と、無理に押さえつけようとしてしまうこともあるのではないでしょうか。
すると、フタをされた状態の不安感情はどうなるでしょう。
行き場を失ってしまいますよね。
すると、お腹や頭が痛くなるといった身体の反応や、いらいらして怒りっぽくなったりというような反応がでてしまうことがあるのです。

自分の気持ちを大切にする
では、「不安」な気持ちを増大させすぎず、上手につきあっていくにはどうしたらいいでしょうか。
そのために大切なのは、まず、不安な感情にも役割があるのだと知っておくこと。
そして不安になったときは、感情が送ってきた自分へのサインだと気づき、冷静にしっかりその気持ちを受け入れること。
ネガティブな感情だからと言って押さえつけず、大切にすることで、どう対処していったらいいのかがわかります。
一旦立ち止まって、確認したり、もし、何かこまったことが起きていたら、誰かに助けを求めたりといった方法をとることができるでしょう。
日頃からマインドフルネスなどを行うことによって、呼吸や身体の状態に気を配っておくことも、とても有効です。

いつも、自分の気持ちを大切に、認めて受け入れていること。
そうすることで、いつも穏やかに、そして生き生きと過ごしていけたらいいですね。
発達障害のある子の子育てのヒントをメルマガでお届けしています
ご登録をお待ちしています
読むだけで心が楽になるEQ子育て 無料メルマガのご登録はこちら