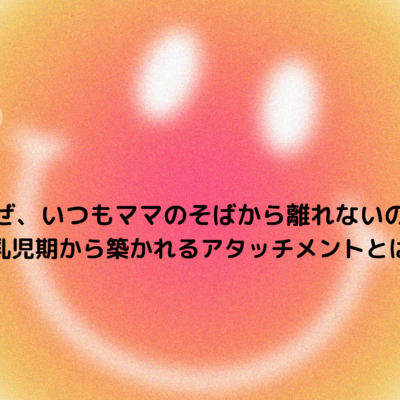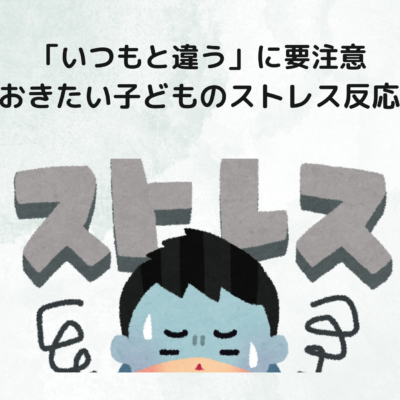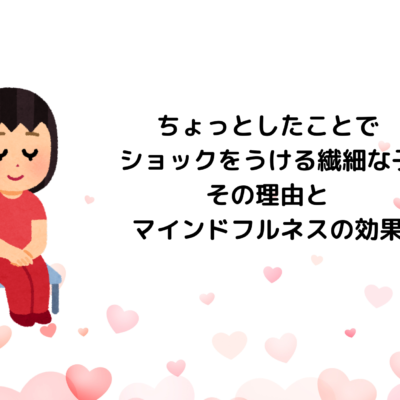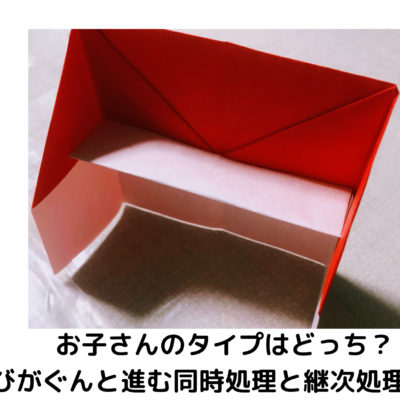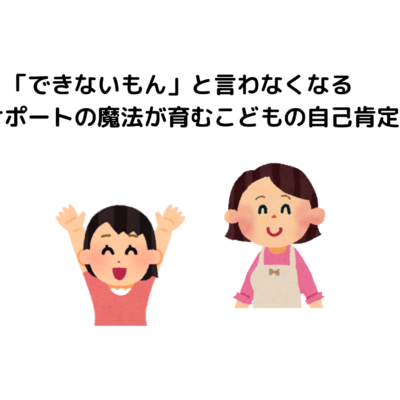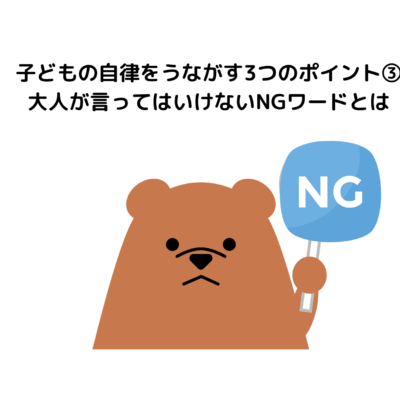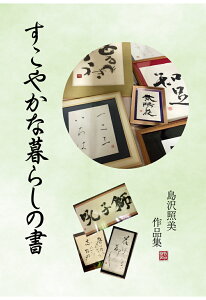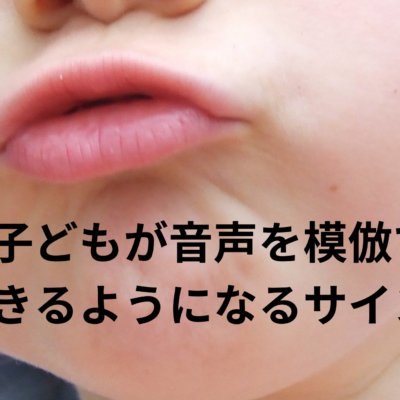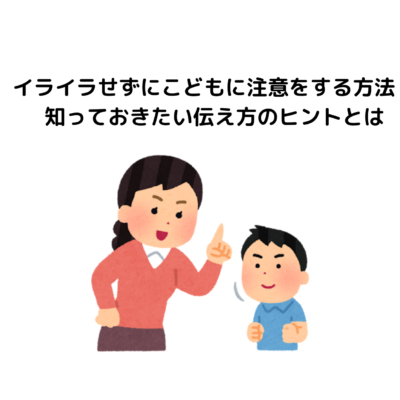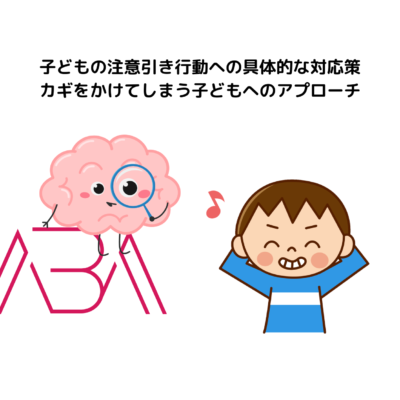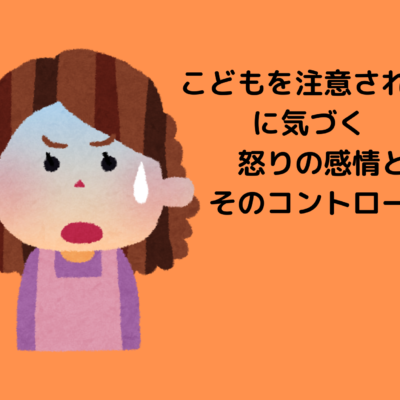こどもが遊んだ後、散らかっている部屋をみるとイライラしますよね。
できればこどもが自分で「お片づけ」をする習慣を身に着けてほしい。
ではどうすれば、こどもが自分で片づけをする力を育むことができるでしょうか。
お片づけが簡単にできること
子どもが自分でできるようにしていくためにまず大切なのは簡単であること。
シンプルにただ入れるだけの収納ボックスをいくつか用意します。
そのボックスの中が見やすいこともポイントです。
つみき、人形、くるまなど、大雑把に分類しておきます。
そこに入れていくだけで、お片づけができる状態をつくりましょう。
お片づけの合図をきめる
遊びに熱中しているときは、こどもはなかなかやめられないですよね。
気持ちの切り替えを促すために、お片づけの合図をつくっておくことが有効です。
リズム音や、好きな曲、タイマーなどお片づけの音を決めましょう。
そして、そろそろ片づけてほしいなというころになったら事前に声をかけておきます。
「ポロポロローンってなったらお片付けの時間だよ」
そして、声がけから30秒ほどたったら合図の音を鳴らします。
「そろそろ片づけなくてはいけないのだな」
と見通しを立てられるようにしておくことが大切なのです。
大人も一緒にお片づけをする
はじめはそれでもなかなか片づけられない子も多いでしょう。
だんだんイライラがつのってきますよね。
「はやく片づけなさいっていってるでしょ!」
と言いたくなるところですが、ここはグッと我慢です。
「ママは車を片づけるから、○○ちゃんは積み木ね。どっちが早く片づけられるかな?」
などのように、お片づけが楽しくなるような雰囲気をつくります。
はじめはそう声がけしてもできないようであれば、大人がほとんどのおもちゃを片づけてしまってもいいと思います。
けれど、かならず最後のひとつはこどもが自分で片づけるようにうながします。
たったひとつであっても自分で片づけたという経験を積ませていくことが大切です。
お片づけは気持ちいいこと
散らかっている部屋には多くの情報があふれています。
目に入るものが多すぎると、意識していなくても脳はその情報をキャッチしてしまいます。
そんな状態だと、大人ももちろん疲れてしまいますよね。
お片づけが終わったら、その時の気持ちを言葉にしてこどもに伝えてあげてください。
「スッキリしたね。片づけると気持ちいいね。」
お片づけをすると気持ちがいい。
その心地よさをこども自身が体感すること。
それがお片づけの力を育む最後のポイントです。
お片づけの力を育むために
こどもに何かを教えていくことは大変です。
おもちゃも大人が片づけてしまったほうが、時間もかからず楽なのです。
子育てはなかなか思いどおりにいかないもの。
いつも必ずこうさせなくちゃいけないと自分を追い込まないでくださいね。
でも、少しずつでも実践することでこどもは必ず成長していきます。
ゆっくりとあせらず、でも着実に、こどものお片づけの力を育んでいきましょう。

発達障害のある子の子育てのヒントをメルマガでお届けしています ご登録をお待ちしています 読むだけで心が楽になるEQ子育て 無料メルマガのご登録はこちら